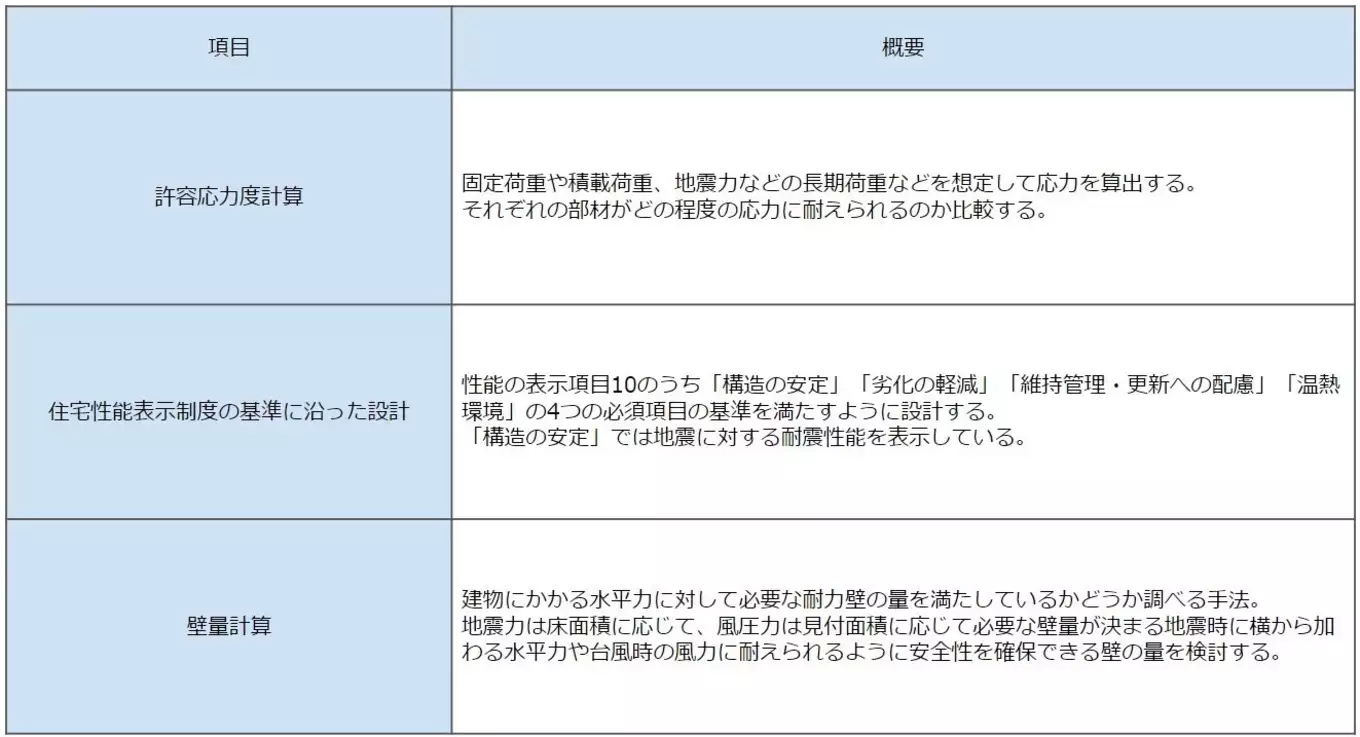耐震構造とは

耐震構造は地震対策ができる構造の中で最も一般的な方法で、現在の建築基準法に沿って建てられた住宅は耐震構造に対応しています。
耐震等級とは

した。下記のように3段階に分けられており、それぞれ明確な基準が設けられています。
耐震等級1
・極めて希な(100年に1度程度)地震力(震度6~7程度に相当)に対して倒壊や崩壊等しない程度
・希な(数十年に1度程度)地震力(震度5程度に相当)に対して住宅が損傷しない程度
・建築基準法で最低限満たすべき基準とされている
耐震等級1は、建築基準法で定められている最低限の耐震水準です。震度6~7程度の地震で倒壊や崩壊はしませんが、一定の損傷は許容しています。そのため、大きな地震が来た場合には、修繕や建て替えが必要となる可能性があります。
・希な(数十年に1度程度)地震力(震度5程度に相当)に対して住宅が損傷しない程度
・建築基準法で最低限満たすべき基準とされている
耐震等級1は、建築基準法で定められている最低限の耐震水準です。震度6~7程度の地震で倒壊や崩壊はしませんが、一定の損傷は許容しています。そのため、大きな地震が来た場合には、修繕や建て替えが必要となる可能性があります。
耐震等級2
・耐震等級1で想定している1.25倍の地震に耐えうる強度がある
・災害時に避難施設となる病院や学校の基準
・長期優良住宅に認定するには耐震等級2以上が必要
・災害時に避難施設となる病院や学校の基準
・長期優良住宅に認定するには耐震等級2以上が必要
耐震等級3
・耐震等級1で想定している1.5倍の地震に耐えうる強度がある
・災害時の拠点となる消防署や警察署などの基準
「R+house浜松中央・藤枝」は全棟で耐震等級3が標準仕様となっており、地震に対する備えができている注文住宅を提供しています。
耐震等級が高い家に住むメリット
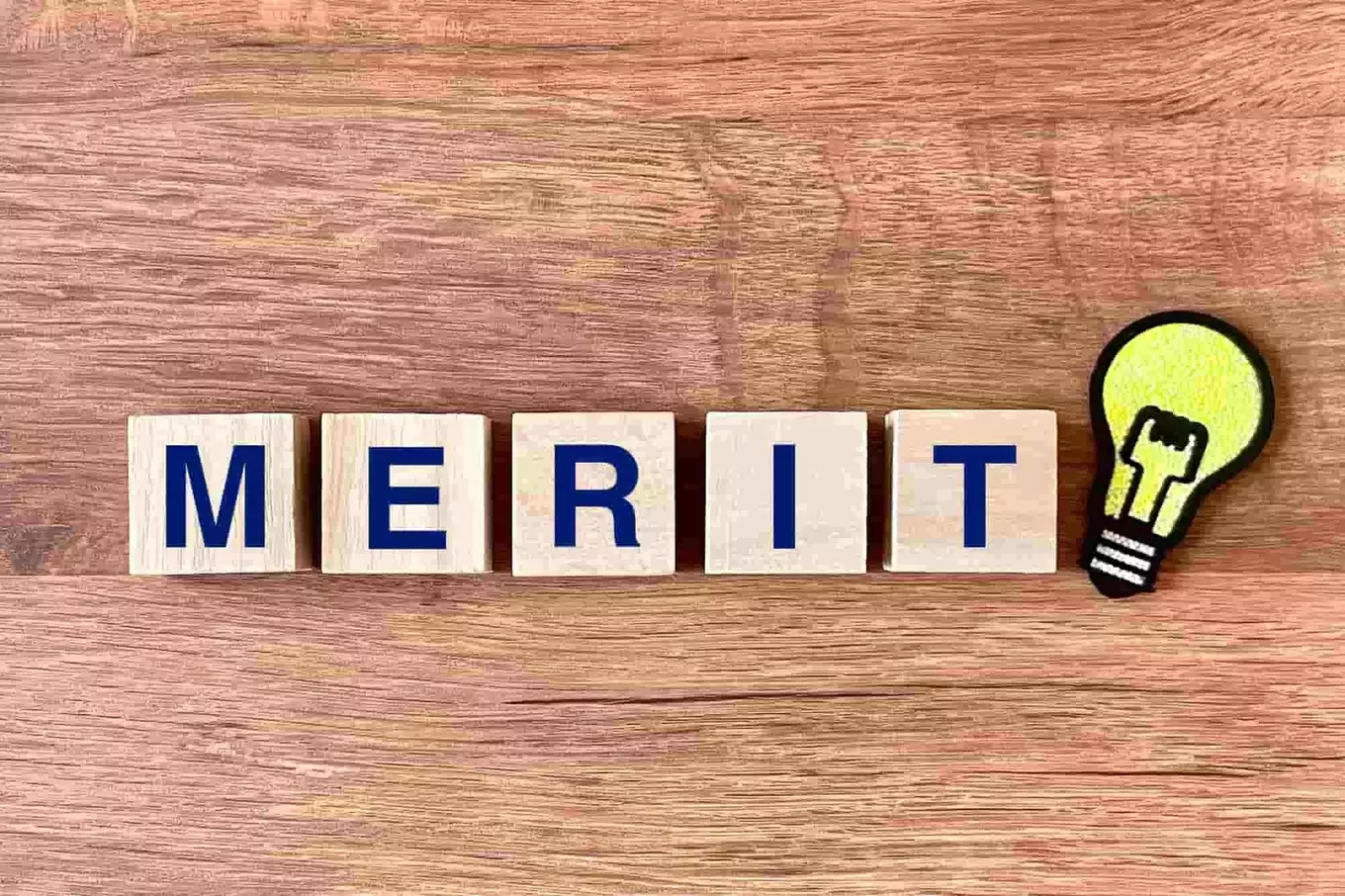
地震や自然災害に備えて安心して暮らせる
住まいに求められる重要な役割は家族や資産を守り、安心して暮らせる環境を整えることです。耐震等級が高いと、その分地震に対してしっかりと備えることができます。
耐震等級2は耐震等級1の1.25倍、耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の耐震性能があります。耐震等級3は耐震性能の中で最も高いレベルであり、大きな地震が起きても軽微な修繕のみで住み続けられる状態を想定しています。
住宅へのダメージが少ないと日常生活を取り戻しやすく、災害時の負担を軽減することができるでしょう。
耐震等級2は耐震等級1の1.25倍、耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の耐震性能があります。耐震等級3は耐震性能の中で最も高いレベルであり、大きな地震が起きても軽微な修繕のみで住み続けられる状態を想定しています。
住宅へのダメージが少ないと日常生活を取り戻しやすく、災害時の負担を軽減することができるでしょう。
地震保険が安くなる
新築住宅を購入するときに火災保険と併せて地震保険への加入を考えている場合は、耐震等級が高いと地震保険料が安くなります。